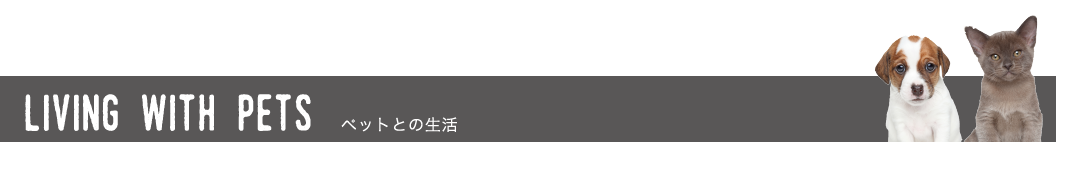

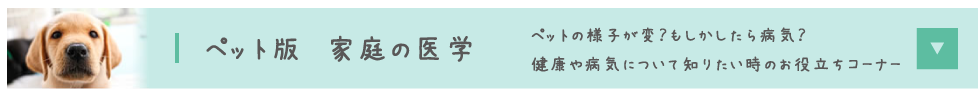
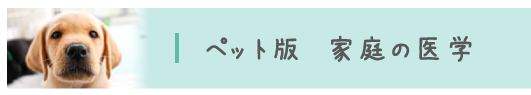
第25回 食欲がないときの対応


第24回 猫のフィラリア症について


第23回 ペットに与えてはいけない人の食べ物


第22回 白内障について


第21回 夏の食中毒について


第20回 腎臓病について


第19回 “パテラ”ってなに? ~膝蓋骨脱臼について~


第18回 うちの子“でべそ”なんだけど…~臍ヘルニア、鼠径ヘルニアについて~


第17回 トゲを踏んでしまったときの対処法


第16回 ペット用救急箱を作ろう


第15回 シニア犬のケア


第14回 皮膚を痒がっているときの対応


第13回 トイレの状態をチェックしよう! ペットのおしっことうんちについて


第12回 おうちでのお薬の与え方


第11回 爪の切り方と深爪をしたときの対処法


第10回 ペットが溺れたときの対処法


第9回 どうして食べてくれないの? 食欲のない猫について


第8回 冬場に多い、ペットのやけど


第7回 垂れ耳の子は特に要注意!ワンちゃんの外耳炎について


第6回 歯みがきの重要性


第5回 心臓マッサージを知っておこう


第4回 電気コードをかじって失神! ペットの感電事故について


第3回 夏に気をつけたい ペットの熱中症について


第2回 何度も戻しちゃうんだけど、どうしよう?ペットの嘔吐について


第1回 何か変なもの食べちゃったかも! 愛犬の誤飲・誤食について




いつも何でもおいしそうにフードを食べていたペットが急に食べなくなったら、とても心配ですよね。もしペットの食欲がなくなったら、どうしたらいいのでしょうか。

ご飯を食べなくなる原因はいろいろ考えられます。食べてもらうためにはまず、なぜ食べなくなったのかを探ってみましょう。
●病気が原因の場合
食欲以外にも体に不調がある場合は、何か病気の可能性があります。
吐き気や下痢など消化器の症状も伴うようであれば胃や腸などの異常が疑われます。
発熱がみられたり元気もなくぐったりしているときには、感染症や内臓の病気があるのかもしれません。
その他、体のどこかに痛みがある場合や、めまい・てんかんなどの神経症状がある場合も食欲はなくなってしまいます。
また、口の中や喉の痛み、嗅覚に異常が生じた場合は、食欲があっても食べられなくなってしまうことがあります。フードの前に行くものの食べない場合や、よだれで口の周りが汚れていたり、口臭がきつい場合は口腔内の異常が疑われます。
食欲不振の他に何か少しでも体の変調が見られたら、すぐに動物病院に連れていきましょう。
●病気以外が原因の場合
食欲以外に特に症状がない場合は、病気以外の可能性もあります。
例えば、引っ越しや模様替えなどで生活環境が変化したり、来客や雷、外からの騒音など、何らかのストレスがかかることでペットの食欲は低下します。
また、トリミングサロンやドッグラン、動物病院などに出かけた後も精神的・肉体的に疲れてしまって食欲が落ちることがあります。逆に全く運動しない日もお腹が空かないので食べないこともあります。
メスのペットの場合は、発情中のときにホルモンバランスが崩れるために食欲は低下します。
さらに、今食べているフードに対して何かしら気に入らないことがあって(フードに飽きた、フードを食べているときに嫌なことがあった、フードの品質が悪くなった、等)急に食べなくなる、ということもあります。
子犬や子猫の場合、一食食べないだけでもすぐに低血糖になり体調が変化してしまうので、食欲が落ちたらすぐに動物病院に連れていきましょう。
成熟したペットで病気以外のときは、一日程度様子を見ても大丈夫です。食欲がなくなる前にどんなことがあったのか、何が原因なのか、よく観察して対処しましょう。
ただし、食べない状態が長く続くと低栄養、低血糖になり、痩せてきて毛づやも悪くなり、免疫力も低下して本当の病気になってしまいます。一日様子を見て食欲が回復しない時には、やはり動物病院で診てもらうようにしましょう。

食欲を出すために家でもできる工夫があります。少しでも食べてもらいたいときには次のことを試してみましょう。
●フードを温める:人肌程度にフードを温めると美味しい匂いが立つため、食欲が出てくることがあります。あまり熱くすると栄養成分が壊れてしまうため、60度以下くらいを目安にしましょう。
●フードを柔らかくする:ドライフードにお湯をかけてふやかしたり、ウェットフードにするなどして食感を変えることによって食べてくれることがあります。高齢ペットなどで噛む力が弱くなっているときには効果的です。
●開封したてのフードを与える:特に猫は脂肪の酸化臭に対して敏感で食べなくなることがあります。フードはなるべく小分けになっているものを使い、一度開封したものは乾燥剤を入れて密封したのち、早めに使い切るようにしましょう。
●食器や置台の高さを変える:食器の形状や材質のせいで食べづらい、ということがあります。噛む力が弱くなっている場合は舌で舐めとりやすい平皿に、逆に舌の出し入れがしづらい場合にはウェットフードを山形に盛れるような容器にしてみましょう。また、食器の高さも背骨と頭が同じ高さになるくらいのほうが食べやすく飲み込みやすいので、個別に調整してあげましょう。
●フードの味を変える、新規食材をトッピングする:今食べているフードに飽きてしまって食べなくなってしまったときには、新しいフードに変えてみたり、肉や魚をトッピングすると再びよく食べるようになることがあります。しかし、それを頻繁に行っていると美味しいものを食べたいために食べなくなることもあるので、エスカレートしないように気をつけましょう。
ペットが美味しそうにごはんを食べているのは、心身共に健康である証拠です。いつまでもそんな姿を見ていられるように、ちょっとした変化にも気付いてなるべく早く対処してあげましょう。
